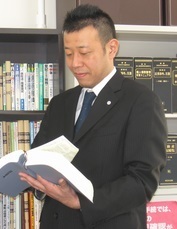〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2-8 YS新大阪ビル6F
受付時間 | 10:00~19:00 (事前予約にて23:00まで対応可能) |
|---|
定休日 | 土日祝(ただし、事前予約にて対応可能) |
|---|
相続登記(不動産の相続による名義変更)
不動産の所有者が死亡した際、その名義を相続人へ変更するためにおこなうのが相続登記です。
相続登記は相続人が自分でできないこともないのですが、複雑な書類をまとめなければならず、司法書士に依頼される方がほとんどです。
「相続登記はしなければならないものですか?」
と質問されることがありますが、相続登記は、相続税申告のようにいつまでにしなければならないといった規定はありません。
相続登記をしていなかったとしても、何か罰則があるわけではありません。
しかしながら、何代も前の名義人のまま放置されていて、いざ不動産を売却しようとした時に相続登記をしなければならず、
大変ややこしくなってしまう事案を多数見てきました。
何代も前からの相続登記をするにあたっては、当然相続人の範囲も広がっています。
相続人調査に相当の時間を費やし相続人を確定したものの相続人と連絡がつかなくなっていたり、
相続人が認知症になっていたり、遺産の争いが勃発して遺産分割協議がまとまらなかったり・・・。
相続登記をするのに膨大な時間と費用をかけることになりかねません。
後の紛争を未然に防ぐためにも、早めに相続登記を行っておいたほうが無難です。
遺言書の有無と遺産分割協議
相続登記といいましても、その登記申請の方法にはいくつかバリエーションがあります。
①遺言書がある場合
有効な遺言書がある場合は、基本的には遺言書どおりに登記を行います。
遺言書がある場合でも相続人全員の同意によって遺産分割協議をすることも可能です。
②法定相続分で登記をする場合
遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合、相続人全員で登記名義人になることも可能です。
その場合は、各相続分に応じて「持分2分の1大阪太郎 持分2分の1東京花子」のように登記します。
③遺産分割協議による場合
相続人全員の合意により、その不動産の取得者を決定します。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員で実印を押印し、印鑑証明書を添付し相続登記を行います。
各バリエーションに応じてそろえる書類が異なります。
公正証書遺言の場合はその正本が必要、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所による検認手続も必要です。
司法書士は相続登記の専門家です
司法書士は登記手続の専門家です。
専門家にご依頼いただくメリットは、なによりも安心であること、そして正確かつ迅速であることでしょう。
司法書士いまよし事務所では戸籍、除籍、原戸籍、住民票の収集から相続人調査、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、相続登記申請まで相続人の代理人として手続を行いますので、安心してお任せいただけます。
もちろん、経費削減のため戸籍や住民票はご自分で準備していただくということも可能です。
不動産の相続登記についてもっと詳しく
とりあえず、相続人全員の名義で登記しておこうか、と安易に考えていませんか? その安易な相続登記が後々やっかいなことになるかもしれません。
不動産の相続登記には被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍や住民票など様々な書類が必要です。
司法書士に依頼するといくらぐらいかかるのかよくわからないと思いますので、相続登記の場合の費用計算例を載せました。
建物の登記がされていないまま放置されていることがあります。相続登記をしようと思って調査をしたところ判明することが多いです。
被相続人の相続開始後、さらにその相続人の相続が開始している状態を数次相続といいます。相続登記の方法は?
明治時代や大正時代に登記された抵当権が残ってしまっている状態を休眠抵当権と呼びます。抹消登記の方法はは少々複雑です。
不動産の相続登記手続きの流れ
ご相談・概算御見積(ご相談時には御見積出来ない場合もあります)
まずはご相談ください。
ご相談には、相続の対象となる不動産の権利書か登記簿謄本、固定資産税の納付書などをお持ちいただけますとスムーズです。大まかで結構なので、相続関係者(子ども、配偶者、ご両親、兄弟姉妹)がわかるようにメモをしておいていただけると概算の見積もりもしやすくなります。
ご依頼に応じて、除籍、原戸籍、住民票、固定資産評価書等の取得、相続人調査
ご依頼に応じて、必要な戸籍や住民票、固定資産評価証明書を取得し、相続人の調査を行います。遺言書が残されていないかどうかを公証人役場で検索する手続も対応しております。もちろん、戸籍関係は相続人様ご自身で取得されるという場合は費用がその分お安くなります。
遺産分割協議書等の必要書類作成と相続人様の押印
どのような形で相続登記をするのかを話し合っていただきます。相続人全員で共有名義にする方法や、ある相続人が単独で取得するのかなどを決定していただき、必要に応じて遺産分割協議書を作成いたします。遺産分割協議書によって相続登記を行う場合は相続人全員の実印での押印と相続人全員の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になります。また、相続人様のご本人様確認も併せて行います。
相続登記費用のお支払、法務局へ相続登記申請
相続登記申請には登録免許税という税金がかかり、登記申請の際に収入印紙で納める必要があります。不動産の評価額が高額になるとこの登録免許税額も高くなりますので、原則費用をいただいてから登記申請を行います。
登記完了後、新しい権利書(登記識別情報)、登記簿謄本、登記完了証のお渡し、お預かり書類、戸籍等のご返却
管轄法務局にもよりますが、通常1週間から10日ほどで登記は完了いたします。登記が完了しましたら、新しく発行された権利書(登記識別情報)、登記完了証、登記簿謄本、戸籍関係書類をお渡しいたします。
| お気軽にご相談ください |
| 06-6195-3470 |
| 受付時間 : 10:00〜19:00 |
不動産の相続登記の費用について
不動産の相続登記の費用について
同一管轄で不動産2筆、固定資産評価額3,000万円まで。以後、不動産1筆追加ごとに10,000円を加算。
さらに他管轄の申請がある場合、不動産2筆までは、35,000円、以後不動産1筆追加ごとに10,000円を加算。
他に、下記実費が必要です。
(例)
不動産は同じ場所にある土地、建物。相続人が、配偶者、子2人で遺産分割協議を行い、
配偶者が不動産を相続する場合の相続登記費用。
土地、建物の固定資産評価額合計が1,000万円、特に出張等なしの場合。
戸籍3通、除籍・原戸籍2通、住民票(除票、住民票)2通、固定資産評価証明書1通も
当事務所で取得したとき。
相続登記報酬 60,000円
遺産分割協議書、相続関係説明図 20,000円
戸籍、除籍の取得5通×2,500円=12,500円
住民票2通×2,500円=5,000円
固定資産評価証明書1通×2,000円=2,000円
登記事項証明書の事前確認2通(インターネット)×1,000円=2,000円
登記完了後の登記事項証明書2通×1,000円=2,000円
報酬合計103,500円 となります。
これに実費として、
登録免許税 評価額1,000万円×0.4%=40,000円
戸籍 3通×450円=1,350円
除籍原戸籍2通×750円=1,500円
住民票2通×300円=600円
固定資産評価証明書2件×300円=600円
郵送、交通費 3,000円程度
消費税8,280円
実費合計55,330円
総合計 158,830円
となります。
- 登録免許税 不動産の固定資産評価額の 0.4%
- 登記簿謄本 600円/通
- その他 交通費・郵送費
お気軽にご相談ください

| 受付時間 | 10:00~19:00 (事前予約にて23:00まで対応可能) |
|---|
| 定休日 | 土日祝 (ただし、事前予約にて対応可能) |
|---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
大阪・淀川区の司法書士いまよし事務所が運営する『大阪相続相談サポート室』では、
相続・遺産整理、遺言、成年後見でお悩みの方お一人お一人に、親身になって無料相談を実施しております。事務所は西中島南方駅徒歩1分、新大阪駅徒歩8分。
一人で悩まずに、まずご相談ください。
| 主な対応地域 | 大阪府(大阪市、吹田市、箕面市、池田市等)、 兵庫県(宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、明石市等)、 京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県 |
|---|
お気軽にご相談ください

お電話でのお問合せ
電話・メールでのご相談は無料です
<受付時間>
10:00~19:00(事前予約にて23:00まで対応可能)
※土日祝は除く(ただし、事前予約にて対応可能)
サービス案内
事務所紹介
司法書士いまよし事務所
住所
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2-8 YS新大阪ビル6F
受付時間
10:00~19:00(事前予約にて23:00まで対応可能)
定休日
土日祝(ただし、事前予約にて対応可能)
知っておいて損はない
相続の基本
知っているようでよくわからない相続のことをわかりやすく解説